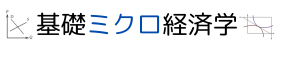一般均衡理論で言えること言えないこと#
この章では,厚生定理を除いたワルラス均衡の様々な性質について紹介する.
窮乏化成長#
市場均衡分析の応用では豊作貧乏というものを学習した.いわばたくさん財が取れたとしても生産者の利益は減るかもしれないということである.これの一般均衡バージョンとも言えるのが窮乏化成長である.ここでは純粋交換経済バージョンを紹介しよう.
(純粋交換経済バージョンの)窮乏化成長とは,簡単に言えば,初期保有が増加したときに,市場均衡において,その消費者の効用が減少するかもしれないということである.
Fig. 45 窮乏化成長の図解#
このロジックは豊作貧乏と同じである.純粋交換経済とは簡単に言えばいらない財を売って,いる財を買うことである.その人の所得はいらない財をどれだけ持っているかとそのいらない財の価格で決まる.いらない財がものすごく増えた場合には,いらない財の価格が下がってしまうので,結果としてその人の所得が減少することがある.そうするといらない財なのでたくさん消費しても嬉しくない一方,売っても大したお金にならない.その結果として効用が下がってしまうのである.
ワルラス均衡とコア#
ワルラス均衡にはパレート効率的という性質があった.これを言い換えると,ワルラス均衡の配分からどこか別の配分へ変えると誰かが損するということである. ワルラス均衡は市場均衡とも呼ばれるので,非常に分権的(つまり人が好き勝手に行動する)もののように聞こえる.一方で,厚生定理によって社会主義の観点からもワルラス均衡は評価できる.
例えば社会が全国民による会議で社会を運営していたとしよう.つまり会議で誰がどれだけものを買うかを決めるのである. 会議の決め方ルールは全会一致ルールであるとしよう. このとき,この会議で決まる配分として,ワルラス均衡の配分は申し分ない.ワルラス均衡の配分からどこか別の配分へ変えようとしても,誰かが損してしまうので,その損する人が反対することになる.よって,一度配分がワルラス均衡の配分として会議で決まってしまえば,これ以上は変わらない.
さて,全会一致ルールだとしても,不満がある人がいるかもしれない.そういった場合,不満がある人同士で連れあって新しい独立国を作ってそこの経済の中だけで取引するかもしれない.パレート効率的な配分にはこういうものが存在する.例えば,AさんとBさんとCさんの3人がいて,Cさんだけが全てを独占するような配分はパレート効率的だが,AさんとBさんには不満が溜まる.そうなら,Cさんをハブって,AさんとBさんだけで彼らの初期保有を持ち寄って独立経済を作る.そうすると,彼らの効用は改善する.このような元の配分から離脱して独立し,彼らの初期保有だけで新しい経済を作ることが離脱する全員にとって得になるようなことがない(残される側のことは考えない)とき,元の配分をコア配分と呼ぶ.コア配分の集合をコアという.
コアについてもう少し詳しい理解をするために,アダム,イヴ,ノアの3人が物々交換をする経済を考えてみよう.財は「ウマ🐎」,「バイソン🦬」,「ラクダ🐪」の3種類であるとしよう.アダムは「ウマ」を,イヴは「バイソン」を,ノアは「ラクダ」を所有しているとする.
それぞれの好みは以下の通りであるとする:
アダム: 「バイソン」>「ウマ」>「ラクダ」
イヴ: 「ウマ」>「ラクダ」 >「バイソン」
ノア: 「バイソン」>「ウマ」>「ラクダ」
この物々交換の結果,アダムがラクダ,イヴがウマ,ノアがバイソンを得ることになったとしたらどうだろう.このとき,アダムは元々持っていたウマよりも好みでないラクダを持つことになる.したがって,アダムはこの物々交換経済から抜け出して一人でウマの世話をしたほうが良い.離脱したい人・あるいはグループがあれば「コア配分」ではないということだったので「アダムがラクダ,イヴがウマ,ノアがバイソン」という配分はコア配分ではない.
次にアダムがウマ,イヴがラクダ,ノアがバイソンを得ることになればどうだろうか?このとき,アダムもイヴもノアも一人で抜け出したところで良くはならない.アダムはウマを元々持っていたので,この経済を抜け出しても変わらない.イヴとノアは元々持っていたものより良いものを得ているので彼らは一人で独立しても損するだけである. しかし,グループでの独立はうまくいく.例えばアダムとイヴが組んで「アダムがウマ,イヴがラクダ,ノアがバイソン」を拒否しノアをハブって独立する.その上でアダムとイヴが元々持っていたウマとバイソンを交換すればどうだろうか.そうすると「アダムがバイソン,イヴがウマ,ノアがラクダ」という配分を得ることになる.これは独立したアダムとイヴの間では「アダムがウマ,イヴがラクダ,ノアがバイソン」よりも良い.したがって,あるグループが独立したいということになるのでこの配分もコア配分でない.
コア配分の一例は「アダムがバイソン,イヴがウマ,ノアがラクダ」である.この場合誰がどう組んでもこれよりも良くなることがないことが示せる.実際,アダムとイヴはベストな財を得ているので,この配分を拒否しようと思わない.ノアは最悪の財を持っているがこれは元々自分が持っていたものなので,一人で離脱したところで変わらない.ノアはアダムかイヴと組もうとしても,彼らはノアとの連合を拒否する.なぜならノアと組んだところで彼らはそれぞれ「アダムがバイソン,イヴがウマ」より良い結果にならないからである.よってどの連合をもってしても「アダムがバイソン,イヴがウマ,ノアがラクダ」を拒絶しても得しない.従ってこれがコア配分となる.
さて,元々の純粋交換経済の話に戻ろう.純粋交換経済におけるコア配分はFig. 46の図中の紫の線で書き表される.まず,コア配分がパレート効率的であることに注意してほしい.もしそうでなければ「全員」というグループによって元々の配分を拒否できるからである.そして,コア配分は初期保有よりも良いものでなければならない.そうでなければ一人でこもって初期保有を消費していればいいからである.
Fig. 46 コア(図中の紫の線)の図解#
さらにもっと言えば,ワルラス均衡の配分はコア配分である.これを見るために二人のケースで考えてみよう.ワルラス均衡の配分から離脱する人がいるとすれば一人だけによる離脱である.なぜなら,ワルラス均衡の配分はパレート効率的なので,二人で離脱しようとしてももう一人は必ず反対するからである.さて,一人で離脱したところで,持っているのは元々自分の持っていた初期保有である.ワルラス均衡では初期保有をそのまま消費するよりも良い生活ができる.なぜなら,初期保有は純粋交換経済でいつでも消費できる配分だからである.誰とも財を交換しないのは市場経済の中でもできるのである.ワルラス均衡では市場経済でベストを尽くしている.ベストを尽くしているということは,誰とも財を交換したくなければできるし,ワルラス均衡で誰かと財を交換しているなら誰とも財を交換しないのはその人にとってベストではないのである.よって,一人だけで独立してもワルラス均衡の配分からよくはならない.よってワルラス均衡配分はコア配分と言える1.
というわけで,ワルラス均衡配分はただ会議で決まる配分であるということ以上に,その配分では誰も,どんな連合を組んでも独立したくならないという性質を持つ.独立経済を作るというのはある意味で鎖国するということに等しい.自分たちで自給自足でやる,そんな連合を組むということなのだから. したがって,一度開国すれば,(もし鎖国するかどうかの決定がその人たちの全会一致で決まるというなら)再び鎖国することはないということが言える.
さて,ワルラス均衡の配分はコア配分であるが,逆は必ずしもそうとは言えない.しかし,人口が十分に大きければ,コアが一点に収束し,そこがワルラス均衡の配分になるということが知られている.これはコア収束定理と呼ばれる結果である.こちらも,詳細な内容は上級の教科書を参照せよ.
コア配分はある意味安定した社会の配分である.引きこもって外界との交流を断つようなグループがあったとしたら,その人たちの誰かは経済的に損をするということである.そうなのであれば,(そのグループに強制力がなければ)引きこもり集団は現れない.コア収束定理が意味することは,人の数が十分に大きければ,そのような配分はワルラス均衡配分であるということである.(過言であるが)安定した社会ではワルラス均衡配分が成立していると言えば,そういった配分を分析することは理に適うのである.
- 1
人が3人以上いた場合は多少分析が複雑にはなるが,実は厚生定理の証明とほとんど変わらない.より上級の教科書を参照せよ.