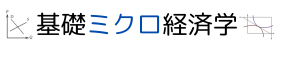個人の意思決定#
前章でも簡単に述べたが,ミクロ経済学のキホンは「個々人の行動をもとに社会の動きを分析すること」である.そしてその個々人の行動は「できる限りで自分にとって最も良い行動」を選ぶことである.したがって,「できる限りの行動」とは何か?その分析対象の人物がその行動についてどう思っているかについてまずは考えないといけない.手順を書くと次の通りである.
手順1. 分析対象の人物ができる限りの行動のリストを作る.
手順2. リスト内の行動についてその人物の良い順に並べる.
手順3. 良い順に高い点数をつける.
点数の付け方はその人物が好ましい行動に高い点数がついていればどんな付け方でも良い.この点数のことを効用と呼ぶ.
例として,回転寿司店に来たX氏のできる限りの行動を考えてみよう.話を単純化するために,次のモデルを考える.
回転寿司店にはメニューがウニ,マグロ,海鮮サラダの3種類であるとする.
ウニは1皿450円,マグロは1皿300円,海鮮サラダは1皿150円とする.
X氏の財布には450円しかない.
X氏は各寿司ネタの組み合わせ(何も注文しないも含む)について,完全なランキングを作ることができる.
このランキングは財布の中身が増えても減っても変わらない.
このモデルにおいて,X氏ができうる行動をリストアップしてみよう.ありうるすべてのパターンを考えなければいけないことに注意である.
ウニ1皿だけ注文
マグロ1皿,海鮮サラダ1皿を注文
マグロ1皿を注文
海鮮サラダ3皿を注文
海鮮サラダ2皿を注文
海鮮サラダ1皿を注文
何も注文しないで帰る
このときにリストにある行動それぞれについて,X氏の好みの順に高い点数をつけていく.仮定よりX氏は完全なランキングをつけることができる.例えば次のように点数をつけたとしてみよう.
X氏の可能な行動のリスト(X氏の財布に450円あるとき)
[4点]ウニ1皿だけ注文
[12点]マグロ1皿,海鮮サラダ1皿を注文
[3点]マグロ1皿を注文
[6点]海鮮サラダ3皿を注文
[4点]海鮮サラダ2皿を注文
[1点]海鮮サラダ1皿を注文
[0点]何も注文しないで帰る
どっちでもいいなら同じ点数をつけても良い.このケースは専門用語で無差別という.ミクロ経済学の大前提として,「個々人は最も良い行動をとる」ということなので,それに従えばX氏は点数(効用)が最も高い「マグロ1皿,海鮮サラダ1皿を注文」することになる.
さて,ここで,X氏の財布に450円ではなく,400円しかなければどうだろうか.このとき,X氏の可能な行動のリストとそれぞれの効用は次のようになる.
X氏の可能な行動のリスト(X氏の財布に400円あるとき)
[3点]マグロ1皿を注文
[4点]海鮮サラダ2皿を注文
[1点]海鮮サラダ1皿を注文
[0点]何も注文しないで帰る
仮定よりランキングは変わらないので点数も変える必要がない.よって,選べる中で最も点数(効用)の高い「海鮮サラダ2皿を注文」することになる. ここからわかることの一つとしては,財布の中身が減ることが全てのネタの購入量を減らすとは限らないと言うことだ.所持金が450円から400円に減ったとき,マグロの消費量は減ったが,海鮮サラダの消費量は増えているのである.行動のランキングは一切変わっていないのにそう言うことが起きるのである.
これがミクロ経済学において,行動がどのように決まるのか,そしてどう言うことが起き得るのかを分析するときの基本である.当たり前のように感じるかもしれない.実際,そういう状況が想定できるならば当たり前のことである.この当たり前の事実から始めて,データなどと合わせて何がどこまで言えるのかを考えることが重要である.データと合わない現象が出てくれば,我々の想定がおかしい.一方直観には反することだが,データでも理論でも言えることは我々の直観がおかしいと言うことだ.そうすれば我々の認識を改め,より良い行動ができるようになる. 以降の章ではこの考え方をベースにして話を進めていく.