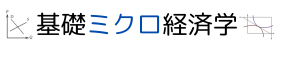独占企業の戦略#
独占均衡#
完全競争の三番目の仮定、「価格受容者であること」はむしろ満たされない場合が多いだろう. 企業は自社製品の価格は自社で決定する場合が普通である.
しかしそうであったとしても無数の企業が競争していればどうだろうか.他社よりも不当に高い価格をつけていればたちまち他社に顧客を持っていかれるだろう.たとえ1社しかない場合でも、潜在的に企業のチャンスがあるならば利益を上げている限り新規参入をしてその企業の利潤を奪うだろう. そのような場合には企業はまるで価格受容者のように振る舞うに違いない.
ここではそのような場合でなく、本当に一社しかない、そして潜在的な参入も考えられない分野を考える.そのような状況を独占と呼ぶ.独占の状況では価格受容者のように振る舞うことは損である.Fig. 20を見てみよう.もしこの企業が価格受容者のように振る舞えば均衡取引量\(q^{*}\)になり、利潤は図中の点AEFで囲まれた部分の面積である.しかしあえて\(q'\)しか生産しなければ価格は\(p'\)までつり上がり企業の利潤は点ABCDで囲まれた部分の面積となる.そうすると少し比較してみればわかるように明らかに利潤は増加する.
Fig. 20 生産量をあえて少なくすることで価格をつり上げる#
数式で見てみよう.企業は生産量を減らすことで価格をつり上げられることがわかっている.需要関数は\(D(p)=d-p\)としてみよう.するとこの関係をひっくり返せば\(p=d-D(p)\)となる.均衡では生産量\(q\)が需要量\(D(p)\)と一致するので生産量と価格の関係は\(p=d-q\)である.(この関係は逆需要関数と呼ばれる) すると企業の利潤は
となる.いま、\(C(q)=c\times q\)としてみよう.ただし\(c<d\) とする.企業の利潤を最大化する生産量は微分したものを\(0\)とおいたものを\(q\)について解くことで得られる.したがってそれを計算すれば
となる.これが独占の時の生産量\(q^{\text{独}}=\frac{d-c}{2}\)である.この時の価格は \(p=d-q\)という関係を使って\(p^{\text{独}}=d-(d-c)/2=(d+c)/2\)となり、これが独占水準での価格である. ところで企業が価格受容者のように振る舞えば\(p=C'(q)\)が成り立つのであった.これを計算すれば完全競争での価格は\(p^{\text{競}}=c\)となる.\(d>c\)であるので明らかに\(p^{\text{独}}>p^{\text{競}}\)となることがわかるだろう.
独占企業ができるのは(生産調整を通じた)価格つり上げ行動だけではない.様々な価格設定戦略をもってして消費者の余剰を吸い上げることができる.次節はそれをみてみる.
価格差別#
前節では独占企業が価格に与える影響を考察した.そこではすべての財は同一の財であれば同じ価格であるという前提に立った議論をしていた.これは一物一価の法則と呼ばれる.一物一価の法則を成立させるためには裁定機会があることが重要である.例えばある消費者Aが10万円でカメラを買おうとしているとき、別の消費者Bが8万円で全く同一のカメラを買う機会があるのであれば、Bが8万円でカメラを買って、Aに9万円で売りつければBは1万円儲けることができる.こういう機会は裁定機会と呼ばれる.転売はこれの最たるものである.裁定機会が徹底していれば売られる価格は全く同一になるはずである.
一方で裁定機会がない状況は現実にたくさんある.例えば地理的に隔たれていれば、例えばX国で買ってY国で売りに行くには非常に費用がかかる.このとき、X国とY国で価格差があっても完全には解消されない.地理的に隔たれていなくても裁定の相手を見つけるのは通常困難である.誰がその財を欲しがっているのか、あるいは誰がその財を手に入れられるかの情報は普通はわからない.このように裁定機会が欠如していれば同一の財であっても価格差が発生することがある. 逆に言えば、裁定機会のないことを利用して、異なる人々に別々の価格で財を売りつけることができるのである.こういったとき、企業はより利潤を大きくすることができる.これを見てみよう.
完全価格差別#
最もかんたんな例として次の状況を考えてみよう. 消費者が二人、アダムとイヴがいるとする.ある企業は彼らに遊園地のチケットを売ることを考える.簡単のため1、どれだけ売っても費用は変わらないとしよう.つまりなるべく収入を多くすることが企業の目的である.
アダムはチケットに8000円支払意思額がある一方、イヴには10000円まで支払意思額がある. さて、 企業はいくらに価格をすれば良いだろうか.
もし価格が8000円なら両者とも買ってくれて収入は16000円である.一方それよりも1円でも高く価格をつけるとアダムは買ってくれない.イヴは10000円までなら買ってくれるのでそれ以上の価格をつけるときには収入は最大でも10000円である.したがって企業は8000円に価格を設定する.
しかし、企業がアダムに売る金額とイヴに売る金額に差をつけて良いとしたらより良い戦略がある.アダムには8000円で売って、イヴには10000円で売るのである.こうすれば両者とも買ってくれて収入は18000円に増加する.これによって消費者の余剰は\(0\)になるがその分企業の利潤が増えるのである. このように各個人ごとに価格を変え、余剰を完全に収奪するような価格差別は完全価格差別あるいは第一種価格差別と呼ばれる.
属性による価格差別#
価格を個人ごとに設定するのは実際には難しい.通常はどの個人がどういった需要を持っているのか、どういった支払意思額を持っているのかを知るのは困難だからである.
この困難を部分的に解消するために、消費者の属性ごとに価格を変えてみることを考えてみよう. パソコンソフトを買うときのアカデミック版などがそうである.また遊園地のチケットにも学生料金などがある.これらは支払意思額が低そうな属性を持つ人には安い価格を、そうでない人には高い価格をつけ、企業が余剰を収奪しているのである.このように人々を属性などのグループに分け、それぞれのグループに対して価格を変えるような行為は第三種価格差別とよばれれる.
非線形価格とバンドリング#
これまで見た価格差別は個人ごとに価格を変えるというものであったが、購入単位ごとに価格を変えるという価格差別も存在する.次の例を見てみよう.
消費者がニンジンを買おうとしている.ニンジン1個に支払ってもいい価格は80円だが、もうひとつ余計に買おうとするときには追加的には40円までしか支払いたくない.それ以上のニンジンは全くいらないとしよう. また企業がニンジン一本を仕入れるのに20円かかったとする.この場合、価格はいくらにすればいいだろうか.
もし価格が40円であれば消費者はニンジンを二本買う.そのときの企業の利益は40円である.もっといい方法がある.80円で売ればニンジンを買うのは一本だが、そのときの利益は60円である.企業は80円をつけるに違いない.
いやもっといい方法がある.二本まとめて120円という価格をつけるのである.このとき消費者はニンジンの2本パックを買うだろう.そのときの利潤は80円である. このようにまとめ売りをするとバラバラに売るよりも利潤を増やすことができるのである.この手の行動は 抱き合わせ(バンドリング) と呼ばれる.
ではまとめ売りを禁止すればいいだろうか.そうしたとしても企業には他の手がある.一本目のニンジンを80円で売って、二本目を40円で売ればいいのである.そうしたら消費者はニンジンをちゃんと二本買ってくれ、そのときの利潤はまとめ売りのときと同じ80円である.こういう価格の付け方は非線形価格と呼ばれる.
似たような発想ではあるが、購入単位ごとに価格を変えずに料金体系を工夫する方法として二部料金制度というものがある.例えば携帯料金や電気料金は定額料金+単価という形をしている. 二部料金を使って企業がどれほど消費者の余剰を収奪できるかを以下の例を使って見てみよう.
消費者は\(q\)だけ電気を使うと\(v(q)\)だけの効用が得られる.一方で全く使わなければ効用は\(0\)であるとする. これに対して企業は\(q\)だけ電気を提供すると\(C(q) \)だけの費用がかかる.余剰を最大化する消費量は\(v'(q^*)=C'(q^*)\)をみたす\(q^*\)である.このときの値を\(p=v'(q^*)=C'(q^*)\)と置こう.これを単価とする. このとき、消費者が\(q^*\)だけ消費することによる効用は\(v(q^*)-p\times q^*\)である. 企業は定額部分を\(B=v(q^*)-p\times q^*\)とする.そうすれば 消費者の効用は最終的に\(v(q^*)-p\times q^*-B=0\)となる.全く電気を契約しない場合と効用値は同じなので契約してくれるはずである.このときの企業の収入は\(p\times q^*+B=v(q^*)\)となる.そこから費用を引いた\(v(q^*)-C(q^*)\)が合計の利潤である. これによると社会的余剰は結果的には最大化されるが、その余剰はすべて企業が奪ってしまうのである.
スクリーニング#
今までの議論は企業が消費者に関する情報(効用や需要関数、支払意思額など)をすべて知っているという前提に立っていた.しかし実際には企業はその情報を得られているとは限らない2.
そこで、各消費者自身に直接その情報を聞いてみようということになる.消費者は自分からそんな情報を教えるだろうか、と思うかもしれないが、ちょっとした工夫をすることで自発的に教えてくれるような行動をとってくれるのである.これを見てみよう.
今、ハンバーガーとドリンクを売ることを考える. 消費者には2タイプいるとする.Aタイプの消費者はハンバーガーには600円の支払意思額、ドリンクには100円の支払意思額がある. Bタイプの消費者はハンバーガーには700円の支払意思額、ドリンクには300円の支払意思額があるとしよう.AタイプとBタイプの消費者はそれぞれ半々の割合で存在するとしよう. 企業にはそういった2つのタイプの消費者がいることは承知しているが、どっちがAでBかはわからないとしてみよう.
まず、普通にバンドリングを使ってセットで700円で売ってみよう. そうするとどっちのタイプの消費者も買ってくれるので収入は平均\(700\)円である.
もっとうまい方法はないだろうか.ここでハンバーガー単品を600円、セットを899円で売ってみよう. そうするとAタイプの消費者はハンバーガーだけを買ってくれる.Aタイプは単品では600円の支払意思額があるが、セットでは\(600+100=700\)円までしか支払意思額がないので899円のセットは購入しない. Bタイプの消費者はセットで899円で買ってくれる.なぜならばハンバーガー単品を購入するとハンバーガー単品には700円の支払意思額があるので効用は\(700-600=100\)である.一方でセットで購入するとセットには1000円の支払意思額があるので効用は\(1000-899=101\)である.それぞれの効用を比較をするとセット購入のほうが大きいのでセットを購入するのである. 収入は\(\frac{600+899}{2}=749.5\)円に増える.このように消費者自身に単品かセットかを選ばせ、その行動により、彼ら自身の情報を引き出しているのである.このように複数の選択肢を用意し、消費者自身に自発的に選ばせることで情報を獲得する行為はスクリーニングあるいは第二種価格差別と呼ばれている.
注目するべきはAタイプの効用は結果的に差し引き0であるが、Bタイプの効用は101円になっていることである.これはBタイプの方が支払意思額が大きいということが効いている.もしAタイプもBタイプも効用が0になるような価格付けをするのなら、BタイプはAタイプのふりをして安く抑えたいと思うだろう.そう思わせないようにBタイプには少しおまけをしてBタイプ用のメニューを選ばせているのである.このように売り手側が情報を知らないことによって比較的高い支払意思額をもつひとが得をする分は情報レントと呼ばれる.