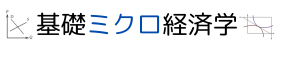公共財市場#
完全市場の第2の仮定は私的消費・私的生産の仮定である.これが満たされない典型的な財として公共財がある.公共財とは次の性質を持つ財のことである.
非排除性:利用を物理的に排除できない.
例としては漁場、公園、道路などがある.
非競合性:複数の人が同時に利用できる.
例としては環境、ネット上の情報、研究成果などがある.
非排除性だけ満たすものを共有地、非競合性だけ満たすものをクラブ財、両方とも満たすものを純公共財と呼ぶ.分類は細かいことだが,これらに共通する点は,自分一人が公共財を買ってきても,他の人までそれを使えてしまうことである.この性質によって,基本的に公共財を市場に任せると、その価値は過小評価されることとなる.
それを説明しよう.簡単のため、次の話を考える.
ある地域に街灯のない街があり夜は真っ暗である.住民は10人おり,街灯が\(q\)個あれば,彼らの効用はそれぞれ\(q\)となるとしよう.街灯の数は\(1\)基まで設置可能である.街灯の価格はひとつあたり3であるとしよう.街灯の価格が3である一方で,街灯が1基ふえたところで,効用の増加分は1でしかない. したがって,この住民の誰もが街灯を購入して設置しようとは思わない.したがって,この住民の効用はすべて0である.
一方で,街灯を1基購入して,その費用を住民全てで割り勘するとしよう.そうすると,一人当たりの負担額は0.3である.その一方,効用の増加分は全ての住民が1であるので,トータルでどの住民の効用も\(1-0.3=0.7\)増加することになる.
つまりすべての住民の効用が改善したので,最初に購入される街灯の量は社会的に最適な水準ではないということになる.もっと言えば,増やせば全員の効用が改善したという事実から公共財の購入量は社会的に最適な水準よりも少ないということになる.なぜそうなるかの直観は単純である.誰かが購入した公共財は自分も使えるので自分が購入しなくてもよく誰か頼みになってしまうという.これをフリーライダー問題と呼ぶ.この問題を解決するには当事者同士がよく話し合い、共同で公共財の購入量を決定するなどが重要である.ただ,話し合いで解決できることも限られる.これは公共財の重要度は人によって違うからである.もし重要だと思うものが多く負担せよとなれば,誰もその公共財が重要だとは言わない.
こういった問題を解決するために,メカニズムデザイン理論と呼ばれる分野が発展した.詳しくは,例えば寺井・肥前「私たちと公共経済」などを参照せよ.
また,公共財が国家規模になると、当事者は全国民となるので話し合いはほぼ不可能である.この場合政府による解決が望まれることになる.