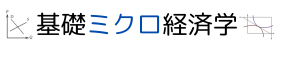経済学における「モデル」#
社会のモデルは単純なものである.実際の社会は複雑だが現実を忠実に複雑なままにすると人々の行動で考えなければいけないことが増えるのでシミュレーションができなくなるからである.また,実際に人間がどのように行動するかについてはわからないことが多いので,いくつかのものごとを仮定する.仮定とは(実際にどうかはわからないけれど分析しやすいように)「〜であるということにする」ということである.多くの経済学の分析では「人々がどのように行動するのか」については「人々は自分にとって何が良いのかの基準を持ち,その基準に従って選べる行動の中で最も良いものを選ぶ」と仮定する.短く言えば「人々は自分にとってのベストを尽くす」ということ.実際にはベストを尽くさない人もいるかもしれないが,ベストを尽くさない人がではどう行動しているかと考えるとキリがないので,特に初歩的な分析ではベストを尽くすものとして考える.これが経済学で最も共通している仮定である.
モデルも仮定であるが,これは現実の大雑把な近似として考える.近似というのは「だいたい世界はこうなっているだろう.細かいところはややこしいので無視する」ということである.世界はもっと歪な形をしているかもしれないけれど,分析に面倒だし,その歪さを真面目に考えたところで結論の細かい部分は変わるかもしれない.しかしそれでも言いたいことはあんまり変わらないだろう.そういうことができれば良い「近似」ができていることになる.言いたいことの大事な部分に注目してもらうということだ1.分析を単純にするために,世界の近似としてモデルを使うのは経済学に限らない.例えば(初歩レベルの)物理学での「摩擦ゼロの物体」,化学における「理想気体」,算数の問題に出てくる「家と学校の間を等速直線運動するタカシくん」などがある.
モデルは分析のために単純化された人工の世界(あるいは箱庭)とも言える.小説などでは「その世界がどのようなものであるか」を明かさないこと(あるいは設定を徐々に明かして謎解きをしていくこと)が作品を深めることになるかもしれない.しかしミクロ経済学(に限らない多くの学問)ではどういう世界を考えているか,そしてどのような設定であるかを(最初にかはともかく)明かしてしまわなければならない.でなければ分析が適切になされているかどうかがうまく伝わらないからである.
それでは,経済学の分析の簡単な例として,以下の単純な「モデル」を考えてみよう.
モデル1
世の中には行動パターンがX個ある.
各個人はそれぞれの行動パターンから利益を得るが,その利益の値は人によって異なる.
それぞれの行動パターンについて,それを選ぶのがベストになるような人を見つけることができる.
人は選べる行動パターンの中から自分の利益を最大化する行動パターンを一つ選ぶ.
人々の利益は大きければ大きいほど良い.
仮定1と2は分析のベースで,どんな世界を考えているのかを設定している.この世界では人は「行動パターン」を一つ選び,それによって利益を得ているという設定なのである.行動パターンが何かは特に指定されていない. 仮定3はいろんな人がいると言っている. 仮定4は行動の基準である.人々がどのような行動を選ぶのかを指定している.経済学ではこの部分は何かしらの「利益」を最大化するとすることが多い.仮定5は価値判断の基準である.つまり,なにを良いと考えるべきかということである.この部分は経済学というより哲学的な話だ.ここでは考えるものが利益しかないので利益を考えている.
モデル1で考える世界では以下の結論を出すことができる:
「人々の行動パターンはどんなものでも禁止しない方が良い」
このような結論になる理由は以下の通りである.もし行動パターンAを禁止したとしてみよう.そうすると,仮定3より行動パターンAがベストになるような人がいる.この人の名前を(なんでもいいけれども)Z氏としよう.Z氏は行動パターンAを禁止されたので別の行動パターン(例えば行動パターンBとしよう)を選択することになる.これはZ氏にとっては行動パターンAよりも良くない選択肢であるので,Z氏の利益は下がることになる.他方,A以外の行動パターンを選択している人は,仮定4よりAが禁止されても選ぶ行動を変えないので,彼らの利益は禁止以前と以後でそのまま変わらない.したがってZ氏のような人々の利益が下がり,彼ら以外の人々の利益はそのままであるので,全体として人々の利益は下がるといえる.仮定5より人々の利益は大きければ大きいほど良いという基準からすれば,行動パターンAを禁止するということは人々の利益を下げるので良くないということになるのである.これはA以外の行動パターンでも同じことであるのでどんな行動パターンを禁止しても人々の利益は下がり,「良くない」.言い換えればどんな行動パターンも禁止しない方が良い.
しかしながらこの結論はモデル1の設定だからこそ言えることであり,例えばモデルを次のように変えれば結論も変わってしまう.
モデル2
人の利益には今の利益と将来の利益がある.
行動パターンには 「授業中に居眠りする」と「授業中に居眠りしない」の二つがある.
人は選べる行動パターンの中で自分の 今の 利益を最大化する選択肢を取る.
人々の今と将来の利益の合計が大きければ大きいほど良い
「授業中に居眠りする」から得られる今の利益は\( 50\),将来の利益は\( -100\)
「授業中に居眠りしない」から得られる今の利益は\( 0\),将来の利益は\( 0\)
さて, モデルがモデル1からモデル2に変わると結論はどのように変わるだろうか?実際にモデル2を分析して確かめてみよう。 まず、このモデルのもとでは 人は授業中に居眠りが禁止されていなければ、授業中に居眠りする。なぜなら 仮定3より人は今の利益に基づいて、それが高い行動を選ぶ。仮定5、6より授業中に居眠りする行動の方が授業中に居眠りしないという行動よりも今の利益が高い。よって今の利益を最大化する「授業中に居眠りする」ことになる。
しかし、このモデルのもとでは人は授業中に居眠りしない方が良い。なぜなら授業中に居眠りすることの今と将来の利益の合計は\(-50\)であるが、授業中に居眠りしないことの今と将来の利益の合計は\(0\)である。仮定4より人々は今と将来の利益の合計が高い方が良いとされているので授業中に居眠りしない方が良い。
さて、最初の結論は「人々は禁止されなければ授業中に居眠りする」次の結論は「人々は授業中に居眠りしない方が良い」であった。この2点 から「授業中の居眠りは禁止した方が良い」,つまり居眠りは叩き起こすべきという結論が導かれる。禁止されなければより悪い「授業中に居眠りする」という行動を取るからである。
これはモデル1より得られた「どんな行動パターンも禁止すべきでない」という結論と対照的である。仮定を変えると結論が変わってしまうことを理解いただけただろうか。
注意して欲しい点として、この仮定がどこまで適用できるのかということである.モデルの話が授業中に居眠りではなく,(授業中かどうかに関係なく)タバコならどうだろうか?アルコールなら?高カロリーな食事なら?バランスの良い食事では?,あるいは危険薬物ではどうだろうか? いずれでもこのような仮定を満たす人はいるだろう。しかしそうであっても実感としては実際にこれら全てを禁止しようとは思わないだろう。ということはモデルの設定にない特徴にこれらの違いを引き立てるものがあるということだ。 モデル化するということは注目されないことを全て捨てることと等しい。捨てられたものの中に重要なものが含まれていることは多々ある。モデル2の分析は「授業中の居眠りを禁止した方がよいこともある」ことを主張するには十分かもしれない。しかし「挙げているものの中で授業中の居眠りだけを禁止すべきで他のものは許容すべき」と主張するにはモデルの設定が足りない。このように何かを主張するにはそれに相応しいモデルを考えなければいけない。
もちろん,どの設定が尤もらしいか,は分析によって変わる.例えば,回転寿司でどのネタを選ぶかを考える人を分析するためには各ネタについて細かく設定したり,データを持ってこなければいけないが,貯金をどれだけするかを考えている人はどちらかと言えば将来についての設定を細かくしなければいけない.回転寿司の分析で各魚の品種や味の違いよりも将来の不安や社会情勢を優先して細かく設定しても謎の社会評論にしかならないし,貯蓄の分析で将来をどのように考えるかの設定を等閑2にしたままマグロの味についての設定を細かくしても仕方ない.