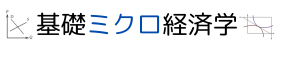消費財と消費者の選好#
消費者が選ぶ財の組み合わせのことを消費バンドルや消費計画、消費プランなどという.どの財をどれだけ消費するかの計画であるのでこのように名付ける. 消費計画すべての集合を消費空間という. 消費者はあらゆる消費プランを検討し、その中で最も望ましいものを選ぶ.
消費プランの例としては次のようなものがある.
1000円をもって回転寿司に行く場合
消費プランはどの皿をどれだけ取るかの組み合わせ
労働と余暇の選択の場合
消費プランは労働時間,余暇の時間,および消費量の組み合わせ
貯蓄問題の場合
毎日どれだけ消費するかの計画
この講義ノートでは簡単のため財の種類は二種類とする.三種類以上あっても議論はほとんど同じである.
さて、人々はすべての消費プランについて効用をもつと仮定する.これは消費プランを比較検討するための数字であり、人々の好みを数値化したものである.つまりはこの効用の数字が最も高いプランを選ぶことが消費者にとって最適な行動となる. 消費プラン \(x\) から得られる効用を \(u(x)\)と書く.このときの\(u\)を効用関数と呼ぶ. 注意事項としては、効用の値自体は重要ではないということである.効用はあくまで選択肢の比較をしているだけの数字であり、その大小関係のみに意味がある.このような性質を序数性と呼ぶ. また、効用の値を異なる個人の間で比較することもあまり意味がない.ただし、なにか共通の指標(お金など)で測るならば意味が出てくる場合がある.支払意思額などがその例である.